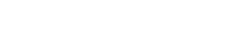HISTORY
薪の歴史

江戸で最多の職業は?

人類が社会を形成し地球を支配していくようになった要素のひとつとして、言葉の使用や道具の発明とならんで火の利用があります。始めのころは焚き火というかたちで、落ちている枝や枯れ木を使っていたことでしょう。次第に人為的に乾燥させたほうが効率がよいことから、今で言う薪というものが登場します。
世界中どの家でも燃料として必要なのは薪(あるいはより高級な炭)でしたから、中世以降都市化が進むと、都市は必ず近郊に森林を抱えていました。山村に住むひとびとは自分たちの燃料として薪や炭を作るとともに都市にそれを運んで代価を得るようになり、都市の発展と薪の製造・運搬の発達は同時に進んでいきます。
近世最大級の都市である江戸の場合を考えますと、徳川家康の江戸入府時には、江戸は交通の要衝ではあったもののそれほど大きな街ではなく、湿地帯が広がる荒れ野が多かったようです。徳川政権は徹底的な治水と干拓、東京湾の埋め立てで江戸城下を大改造し、18世紀初頭には人口100万人、「八百八町」と称する、世界最大とも呼ばれる大都市になりました。
江戸に密集する住宅は、町人のものだけで20万戸くらいはあったと思われ、これらのすべての住居で毎日煮炊きをするわけですから(火災に弱い江戸の町、幕府から暖房用としての使用は厳禁されていました)、江戸の町で最も軒数の多い店は薪炭問屋でした。往来には薪を満載した大八車がひっきりなしに通行していたと思われ、江戸の町でもっともよく見かける職業は薪屋だったはずです。
明治期を迎え、欧米から産業革命の波が押しよせますが、ガスや電気が一般家庭に普及するのは20世紀になってからです。薪は長い間手軽な燃料として親しまれてきましたが、戦後の復興期から高度成長期にかけて、役割を終えていきました。
しかし江戸時代から活躍する薪炭業者は、現代の東京でも元気です。これは東京の特殊事情かもしれませんが、主に西日本で「備長炭」を生産している林業家がまだまだいます。
備長炭はよく見かける柔らかい黒炭と違い、加工に手間と技術をかけた、固い白炭です(打ちあわせるとすんだ高い音が響くのをご覧になった方も多いでしょう)。高価なため、なかなかこれを使う店は少ないのですが、東京には高級料亭が多いので、これを扱うために江戸期より続く薪炭業者が残っているのです。
炭の生産者は必然的に薪も作ります(炭にならない部材も採れるため、これを薪に加工する)。そのため老舗の薪炭業者でいまだに薪を扱っているところがあり、日本の旧来の薪はストーブ用としてはやや細めのため、ピッツェリアが重宝しています。
森は町とともに

この間、江戸に人口が集積すると同時に、江戸の周辺の荒地に農家が多数入殖し、薪の原料としてナラをはじめとする雑木林の育林を進めました。武蔵野のみごとな雑木林はこうした人びとの努力のたまもので、雑木林の育成が江戸の発展とシンクロしていたからこそ江戸は栄えることができたのです。
そして伐採され、利用された里山は、すぐに萌芽更新を始め20〜30年でもとの姿となります。切り株から何本もの芽が出て成長していくので、こうした再生林(2次林)の広葉樹は、指を広げたように、同じ根本から放射状に育っていくのが特徴です。
若い木を必要とし、結果として萌芽更新を起こさせる林業をしてきたのは、シイタケのホダ木とする原木を伐る人たちでした。この人たちにも高齢化の波と、コストとの戦いが深刻ですが、里山の木を伐っている人の多くは、シイタケのホダ木を採っていることが多いはずです。
シイタケのホダ木は薪用に使われるよりもやや若い、20〜25年のナラやクヌギを使います。そのため、幹の細いところをホダ木、太いところを薪と仕分けして使うことがごく普通です。
ホダ木の生産や薪の生産に取り組む林業家は、立木を買って伐採します。伐採を山主さんから頼まれることもあります。前に書いたとおり、東日本では手入れの行き届いた山はナラ山であることが多いのです。
身近なところで自然の力を借りてこうした循環を起こしていけるのも、温暖で四季に恵まれ、植生も豊かな日本ならではです。自然に感謝、森で働く人に感謝、都会で木を使ってくれる人にも感謝です。
町で薪を使う

さて、現代の薪ストーブはめざましい進化をとげ、高効率で高機密(部屋が煙くなったりしない。逆に室内の空気を吸い込んで煙突から放出するので、空気清浄機のようなもの、とも言える)、着火や火力の調整も容易です。
そして特筆すべきは煙突の進化で、現代の煙突は断熱された2重煙突で、触っても熱くありません。つまり煙を冷やさず、熱いまま空中へ放出するように設計されています。
「煙突の先から出る白い煙」実はこれは水分です(水蒸気は目には見えず、見えているのは冷やされて液化した水分)。煙は冷やさなければ目には見えません。そのため、現代の薪ストーブは煙突を断熱し、煙を冷やすことなく空中に放出するようにできています。
それでも煙が白く見える場合、立地環境が悪い、施工の失敗ということもありえますが、原因として最も多いのは薪の乾燥不足です。われわれ薪の生産者は、乾燥のための最大限の努力が必要と心がけています。
薪ストーブの進化もあり、また在来工法以外の住宅(ログハウスなど)の需要が高まったことなどもあり、現在では建築基準法で断熱の配慮や部材など一定の要件をつけて、どこでも薪ストーブが設置できます(ただ、条例で規制している自治体もあります)。
薪ストーブ用の薪の太さはさまざまで、当社でも各種そろうように心がけていますが、手軽に燃やせる細めの薪から一本入れたら半日暖かいような太い薪まで、使うかたのお好みです。
また長さは20〜60cmまでこれもさまざまですが、近年のデータでは、ストーブの指定する最大薪長よりは2回りほど短いもののほうが、炉内の熱いスポットに収まるため効率はよい、とのことです。長いと両側が不完全燃焼を起こしがち、ということですが長く太い薪はなんといっても存在感があり、インテリア、またエクステリアとしてもいいものです。これも考えかたですね。
長い年月を経て、ふたたび都市に「薪屋」の姿があります。里山の環境を守ることは都市の環境を守ること、そして地球の環境を守ることにつながります。里山の環境を守るためには、そこで働く人を経済的に支えなければなりません。
江戸の昔とちがい、今の都会で薪を使ってくれるのは薪ストーブユーザーです(もちろん、ピッツェリアも強い味方です)。森と町をつなぎ、みんなの力で里山を守り、温暖化に対抗するため努力しておりますので、薪ストーブユーザーは胸を張って薪を使ってください。