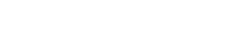ABOUT
薪について


環境のため木をつかう
【東京薪市場】が薪の材料としているのは、北関東と長野県で伐採されたナラ・カシ・クヌギの広葉樹です。これらはすべて「ブナ科コナラ属」というグループに属する木です。
よく誤解されていますが、ナラ、あるいは広葉樹が薪ストーブには必須、ということではありません。現に、薪ストーブの先進国である北ヨーロッパや北アメリカでは、主にマツの仲間などの針葉樹がよく使われています。
しかし薪ストーブユーザーなら、よく「薪はナラに限る」などというセリフを聞いたことがあるでしょう。これにはいくつか理由があります。
まず、火もちがよい。
コナラ属の木は比重が大きいのが特徴です。同じ体積なら、ナラのほうがスギの1.5倍ほどの重量があります。木の組成は樹種に関わらずよく乾燥させ、水分や揮発成分を減少させれば残りは炭素が主成分であり(木炭にすると99.9%の炭素塊となる)、重量によりそこから出てくる熱エネルギーがほぼ決まります。つまり、火力が強く、火もちのよい薪になります。

次に香りがよく、炎がきれい。
「かそけき」香りがコナラ属の特徴です。やはりいい薪であるサクラは、燻製時に用いられることでもわかるように強い燻蒸香が特徴です。また、やはり豊富に出まわるケヤキも、やや刺激臭がします。スギ・ヒノキなどの針葉樹は、単体ではいい香りなのですが、食品とともに嗅ぐといやな匂いに感じることがあります。それらに比べ、コナラ属はかすかな、上品な香りがします。
また、炎のゆらぎも絶品で、心を落ち着かせる効果があるとされる「1/f」のリズムの炎、また「オーロラ燃焼」と呼ばれるゆらぎを実現します。
そして資源として豊富である、ということ。
伐採してしまうと植林が必要な針葉樹と違い、若い広葉樹は「萌芽更新」という活動を行い、切り株から次世代の芽が出て林は再生していきます。つまり、30年までの若い広葉樹の伐採は、われわれが床屋に行くのと同じで、木は死んでいません。勢いよく再生していきます。そのため里山の広葉樹林(雑木林)は30年に1度伐採するのが正しい手入れです。このタイミングで伐採しないと、林は再生しづらくなっていきます。

そして刈り払った明るい地形に強いのがコナラ属であるため、東日本の里山は手入れをすればするほどほとんどがナラ、という楢山、楢林になっていきます。コナラ属より重い木もいくつかありますが、林を作るほど強い成長をするナラはやはり頼もしい木です。
ただ【東京薪市場】は「薪はナラに限る」とは考えていません。どんな木でもよく乾燥させればいい薪です。しかし優秀なコナラ属がふんだんに使える、森林王国日本だからこそ、材として豊富なコナラ属をありがたく使っています。
カーボン・ニュートラルとは

薪を作るためには、典型的には里山の30年くらいのナラ林でそこに生えている木をすべて伐ります(皆伐)。伐る時季は大切で、葉が落ちて、木の中の水分が少ない時季です(本来南国の木であるカシは同じコナラ属でも常緑樹ですが)。シイタケのホダ木を作っている人、変わったところでは枝を使ってソダ(粗朶、木の枝を束にしたもの)を作り、河川や港湾の水質改善のための魚礁(ぎょしょう、人工の魚の巣)として国土交通省に納めている仲間もいて、こういう人たちと協力することがよくあります。直径15〜30cmくらいの幹で作れると効率もよく、きれいな薪が作れます。
原料の丸太を寸法に切って割るわけですが、それだけではまだ薪ではありません。これをよく乾燥させ、含水率(木の木質部分に対する水分の割合)を20%まで落とします。よく16%以下、と特に薪ストーブ代理店が言っているのを聞きますが、これは日本の湿潤な環境では無理で、乾くのが早いか、腐る、もしくは虫に食われるのが早いか、という状態になります。同じように「2年以上乾燥」という主張もあり、もちろんそうすることができればよいと思いますが、やはり菌や虫で台なしになる危険が大きく、そもそも林業の側が資金繰りに耐えられず撤退してしまいます。
乾燥させるための方法は人それぞれです。風とおしの良い場所に積み、上にトタンやシートなどを載せる人。鉄のカゴ(メッシュパレット)に入れて積み上げる人。ビニールハウスに入れる人。要はその人のやり方で20%以下まで落とします。
さて、伐採された木は次の春には切り株から芽を出し、勢いよく再生していきます。この間、木は2酸化炭素を光合成の材料として取りこんでいきます。ですから、薪ストーブユーザーが燃焼によって空気中に放出してしまう二酸化炭素と同程度、伐採後の森林が吸収していく、ということになります。
これがカーボン・ニュートラルの原理で、人類はまだ科学技術で効率的に2酸化炭素を吸収・固定化することはできておらず、海洋面と森林が2酸化炭素を吸収してくれる作用に頼っています。±0、とも言えますが、地中から掘り出した化石燃料を燃焼させて2酸化炭素を大気中に放出することとは根本的に違います。
伐採されずに歳を重ねた森林は、2酸化炭素の吸収の効率も落ちていきます。里山の広葉樹を伐採して萌芽更新を促すことは、森と協力した温暖化対策、ということができます。
楽しく温暖化対策を

温暖化対策のために2酸化炭素を出さない原発を、という主張の人も大勢います。福島県内に用意していた薪が原発事故の放射線で使用不能になり、また大勢の林業従事者が廃業したのを見た経験のあるわたしたち、そもそも地震大国で近い将来必ず巨大地震が日本を襲うと知っているわたしたちは到底こういう考えには同意できませんが、では何もしないのか?と問われる場合もあるでしょう。

われわれの答えは「薪ストーブユーザーは日々、薪ストーブの利用を通して環境問題にコミットしている」ということです。
朝、あるいは夜、薪に火をつけるたびに森を思い、林を思い、そこで生活する人を思う。部屋の灯りを落としてストーブの炎をながめる。お茶を飲んでもいいし、お酒を飲むのもいい。自然について考える時間。たまにはスマートフォンやパソコンからも離れて。
都会で薪を使う時間。心を豊かにする時間です。