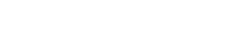NOW
林業の現状


木の種類と生態
よく誤解されますが、スギやヒノキ、マツなどの針葉樹は紅葉樹とは全く別の生態を持つ植物です。
建築材料になるような針葉樹は人間が品種改良した樹木で、自然にまかせてもあのような林にはなりません(「秋田杉」などは本来天然の木をさしていましたが、現在は天然の杉で建築に利用されるものはありません)。針葉樹は基本的には実生(種が落ちて地面から芽が出る)で増える植物ですが、自然に任せてもあのようなまっすぐの木にはならず、すべて人間が育てた苗を植えてあります。すなわち、植林です。
それに対して、若い雑木林は、伐ることによって自然に回復します。ただし樹齢50年を超えるような雑木林は、伐っても萌芽更新をおこしづらくなっています。こうした人の手をはなれた山は従来奥山、もしくは原生林と呼ばれ、実生の芽は高い樹木のつくる日陰によってうまく成長できません。300年で親の木が寿命をむかえ、倒れると、はじめて陽の光が林床にさしこみ、芽は成長しはじめます。つまり、原生林は300年のサイクルで回っています。
都市近郊では林業従事者が減り、いや正確には需要がなくなって林業が成りたたなくなり、高度成長期以後は里山の伐採が止まってしまいました。【東京薪市場】もよく伐採木の引きとりを依頼されますが、首都圏の木はほとんどが60年以上、幹回り50cm以上の巨木です。木を伐る動機が開発に限られるため、萌芽更新を引きだすことができないのです。
また近年、クマなどの野生動物が都市に出現し問題になっていますが、原因の大きな部分はこのことと関係があります。
森と町の境目、すなわち里山が原生林化しているためクマは餌を求めて進んでいるうちに、突然町に飛びだしてしまうのです。手入れをした里山はクマにも人間のテリトリーだとわかるため、里山緩衝地帯となって、クマは奥山に帰るわけです。
里山を原生林と町との緩衝地帯とする、という考えは人間にとって優れた仕組みです。もともと森林に住んで木の実を食べていたであろうわれわれの祖先が平原に出て集落を作り、逆に森林を開発して自分たちで利用したのが里山です。
必要なものを里山からいただいて、森を再生させる。人間には、人間を守り育ててくれた森林を大切にする義務があるのです。
資源大国・日本

日本は国土の7割が森林という森林国家です。そのうちの6割が天然林、4割が人工林です。人工林というのは、通常スギ、ヒノキ、マツなどの針葉樹の植林された林を言います。
里山の雑木林は、通常は人間が植えたわけではないので、天然林に分類されるのが普通ですが、人間が生態に影響を与えているので、原生林に対して2次林、という呼び分けもします。
薪ストーブ用の薪の主役はナラ、それもコナラです。

日本では標高の低いところにコナラ、標高が高くなるとミズナラとブナが共存するブナ・ミズナラ混交林としてコナラと住み分けていたのですが、近来の温暖化の影響で、ブナやミズナラはかなり標高の高いところまで後退しています。ちなみに、コナラ・ミズナラ・ブナの3種ともブナ科コナラ属の木です。クヌギもです。これらは秋に葉を落として冬を越す落葉樹です。
カシは同じコナラ属の木ですが、本来は暖かい西日本に棲息する木で、葉を落とさない常緑樹です。比重がコナラ属中最も大きく、日持ちのいい木です。
カシにも何種類もあるのですが、【東京薪市場】は茨城県に造園業者の林などに商品として人口的に植えられたカシを入れ替えのために伐採したものをよく使います。これらはシラカシです。
他にアラカシなどがあり、やや背の低いウバメカシは西日本の臨海部に多く、備長炭の原料になります。
アカガシというのもありますが、実はこれはシラカシです。環境によって樹皮が赤っぽくなり、昔の人が別の木だと思っていたのでこの名を付けられました。

最近注目されているのが、房総半島の沿岸で林を作っているマテバシイです。マテ貝のような葉をつけていて、シイの実のようなどんぐりを付けるのでこの名がありますが、この木はブナ科の木ですがコナラ属ではありません。見た目はシイよりカシに似て比重はカシよりはやや小さく、ナラと同じくらいです。
やはり良い薪になり、良いかおりがする木で、またドングリにエグ味がまったくなく、アーモンドのような味がする、ということでお菓子や料理の世界からも注目されています。
前にも書きましたが、シイとクリもコナラ属の木ですが、シイ比重が小さく樹皮の見た目がややみすぼらしいこと、クリは比重が小さいことと木質内に小さな気泡をびっしりと持っているため、パチン!とはぜることがあり、あまり好まれません。
あえて言えば、ナナカマドやキリなど燃えにくく、ヤブニッケイなどクスノキの仲間は独特の匂いがします。ただほとんどの木は乾かせば良い薪になり、中でもコナラ属の木が豊富な日本は、薪ストーブに関するかぎり、資源大国と言っていいのです。
森と町の協働
里山の森林の特徴は、地形が急峻であること、個人所有の場合小さな面積に区分されていることです。
実は大規模な林業会社は機械化が進み、若者の就労も増えています。ユンボ、バックホーと呼ばれるパワーショベルに回転式のツメをつけたものなど、操作感がUFOキャッチャーに似て、座席も冷房が効いていたりするので大人気です。
ただ、このような大型機械の入る広葉樹の森林は、大量に伐採してチップ材とし、製紙会社や最近急速に増えたバイオマス発電所に流れていくことが普通です。
里山は面積の小さい区分所有の林で成りたっていて、大型機械で大規模に伐採する、ということには全く向いておらず、小型の機械や人力に頼っての仕事です。
それだからこそ、林ごとに細やかな作業をし、萌芽更新によって早新環境を守ることができるのです。作業の性質上、そんなに利益があがる仕事ではありません。

林業の人手不足と担い手問題
高齢化も深刻で、後継者のいる林業家はごくわずかです。若者の参加を願っていますが、実際にはアジア各地からの若者が出稼ぎにきてくれており、苦労をいとわない彼らの働きに頼っている現場が増えています。
その意味からも最近の排外主義的な風潮にはまったく賛同できません。そのうえで日本の若者にも利益の追求だけではなく自然の中でのびのび働く良さを知ってもらいたいのですが、もちろん収入も大切で、家族も養えないのに林業をしろ、薪を作れとは言えません。

広葉樹伐採と里山の現実
建築材として活用できる針葉樹と違い、広葉樹の場合は「いらないから伐る」という仕事が全体としては多数で、その仕事がチップ製造と結びついています。伐採を依頼されれば伐採料が入り、その上で大型機械で大量に伐った木をチップ工場まで大量に運搬すればコストもかかりますが収入も大きいでしょう。
里山の仕事はそれとはだいぶ違います。人力や小さな機械で作業すれば、1日に伐れる木はせいぜい2〜30本です。そのため、付加価値の大きいホダ木や薪の製造が必要なのです。
ホダ木や薪にするために木を伐る、という面も確かにありますが、里山の環境のために適齢期の木を伐らねばならないが経費がなければ伐ることはできないし、それを仕事にすることもできない。

薪ストーブユーザーと里山をつなぐ循環
そこで薪ストーブユーザーにお金を出してもらい、そのお金で木を伐る。里山の環境は改善し、都会のおうちは薪ストーブで暖かくなる。そして山で働く人や薪をお届けするわれわれは収入をえて仕事を続ける。さらに言えば温暖化対策にもなっている。素晴らしいことだと思いませんか?
われわれはこれを森の人と町の人で協力して里山の環境を守るということだと思うし、まして丸太で購入して割ってくれるお客さんなどは、林業の一部を分担してくれている、と言ってよいと思います。
このように、薪を媒介に薪ストーブユーザーと林業家は環境・エネルギー・温暖化対策に日々関わっています。薪ストーブユーザーの皆さまにも、どうか誇りを持って今日もストーブに火を入れていただきたいと思います。